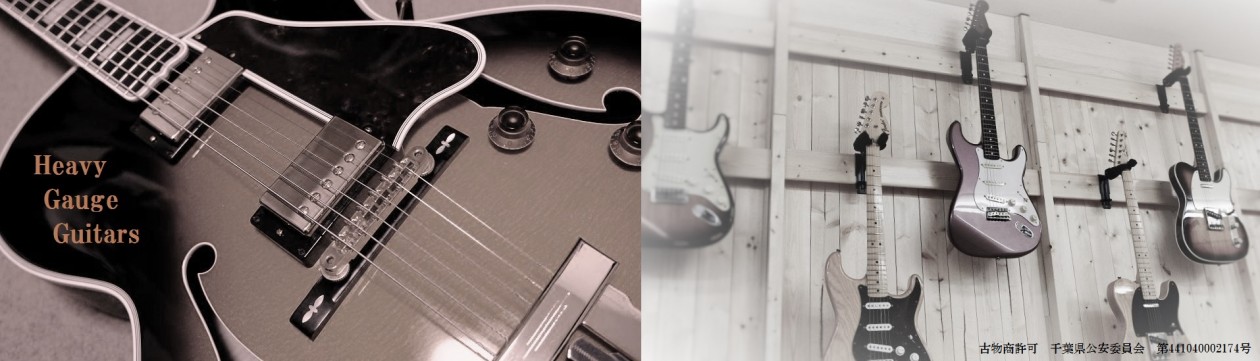上画像はフジゲン期(1993~94年製造)のFender Japan Stratocaster ST57-70です。Heavy Gauge Guitarsにてフレット等のメンテナンスと電気部分は当店考案の「3×3 Way Control」へカスタマイズを実施させていただきました。今回ご依頼主様のご許可を頂き、3×3 Way Control導入の一例として紹介いたします。
3×3 Way Controlというのは3wayのポジションセレクターにもう一つモードセレクターとしての3wayスイッチを組み合わせることで9種類の音色を確保できる配線になります。スイッチ追加のカスタマイズ例は数多あり、スイッチが増えることで直感的な操作からほど遠くなったり、同じサウンドのポジションが複数できてしまったりといったデメリットもありますが、当店の3×3Way Controlの場合は単に音色数が増えるだけでなくそれらが比較的直観的に操れる点が特長です。今回の場合、レバースイッチを5wayから3Wayに変更、センタートーンを3Wayのロータリースイッチに変更し、レバースイッチを「Neck Position」「Mix Position」「Bridge Position」の切り替え、ロータリースイッチを「シリーズ接続(Fat Tone Mode)」「ノーマルシングルコイル(TL Mode)」「ハーフトーンシングルコイル(Bell Tone Mode)」の切り替えを担います。具体的には下表のとおり。
3×3way Controlのポジションニング
|
Rotary Position 3way Position |
Fat Tone Mode |
TL Mode |
Bell Tone Mode |
|
Neck |
F⇒C |
F |
F+C |
|
Middle |
(F+R)⇒C |
F+R |
F+C+R |
|
Bridge |
R⇒C |
R |
C+R |
+・・・パラレル接続(いわゆるハーフトーン)
⇒・・・シリーズ接続(2つ以上のコイルをハムバッキングPUと同様に接続。ただし本機のPUの場合、逆磁極逆巻の組み合わせはないのでハムキャンセルはなし。)