
こちらのプレシジョンベースはFenderのジュニアブランドSquireのもので新品の実売価は3~4万円くらいの価格帯です。このくらいの価格帯になるとメーカーも製造コストがかなり厳しく制限を受けるためか基本的な調整が半端な状態で売られていることが多いと思います。本機の場合、2004年製で製造からの経年変化も加わっているとは思いますが、新品でも本機の元の状態と同様なネック回り・フレット周りであることは珍しくなく、それが原因で初心者さんの練習モチベーションが左右されてしまったりもあると思います。低価格品であってもメンテナンスを加えることで弾き心地は激変し、初心者さんの最初の一本として長く付き合って行ける楽器になり得ます。以下、今回行ったフレット周りのメンテナンスのBefore/Afterを紹介します。



今回のベースの場合、まずフレット浮きの修正を行いました。具体的にはまず浮いたフレットを改めて指板に叩き込む作業を実施。叩いて修正した後しばらくすると再び浮き上がってしまうこともあるので、しばらく時間をおいてから再度チェック、若干ですが再び浮き上がっている箇所があり、そういったところは接着剤を注入して再固定を図っています。「フレットを接着する」というのではなく「フレットが打ち込まれている溝の隙間を埋める」という目的です。フレットに接着剤を使うというのはなじみがない方も多いと思いますが、実はメーカーで制作されている高価格帯のギターでもフレットを打ちこむ際に接着剤を併用している例はたくさんあります。そうしてフレットをしっかり固定した状態でフレットの高さに若干ばらつきがあったので擦り合わせ(フレットを削って高さを揃える作業)を実施。といっても高さの差はわずかでもともと目立つ凹みもなかったフレットなので擦り合わせで削った量はわずかです(0.05mm未満)。そしてフレット両端の鋭い部分を削り落とし(丸め加工)を加え左手移動時の引っ掛かりを解消、最後に脂分が抜けた指板のオイルケアをして完了。ローズウッドやエボニーは脂分が多い材なので、オイルケアも結構大事です。
以下Afterの状態をご覧ください。


今回のメンテナンス例は「新品売価3~4万くらいの低価格機で足りない部分を補って質を大きく向上させる」という例です。メンテナンスの内容としては高級な楽器でも行うもので、買ったばかりの楽器でも「なんか弾きにくい」「なんか音がヘン」といった場合に今回同様の基本的なメンテナンスで化けてくれることはよくあります。お手持ちの楽器でお心当たりがあれば是非ご相談ください。
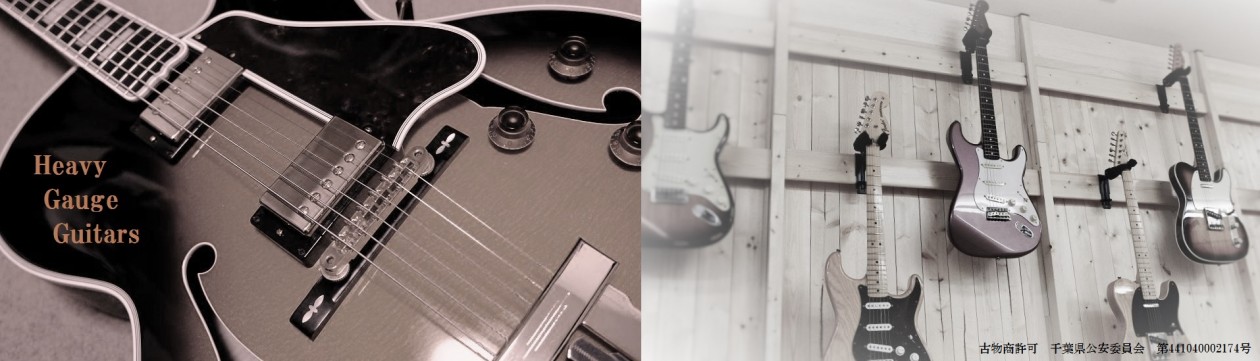


 IbanezのArtist Series、1984年製のAR-300のレストア(しばらく放置されていたものを使える状態に復帰)させていただきました。画像左が作業前、右が作業後です。今回はピカピカに再生するのではなく、古さを残しつつ演奏性を回復させるのと、違和感のある破損個所を補修するという方向性です。幸い電気系統は現役で使える状態でしたが、フレット周りの劣化が顕著で、ヘッドエッジ欠けなどがありました。以下レストア作業の詳細。
IbanezのArtist Series、1984年製のAR-300のレストア(しばらく放置されていたものを使える状態に復帰)させていただきました。画像左が作業前、右が作業後です。今回はピカピカに再生するのではなく、古さを残しつつ演奏性を回復させるのと、違和感のある破損個所を補修するという方向性です。幸い電気系統は現役で使える状態でしたが、フレット周りの劣化が顕著で、ヘッドエッジ欠けなどがありました。以下レストア作業の詳細。
